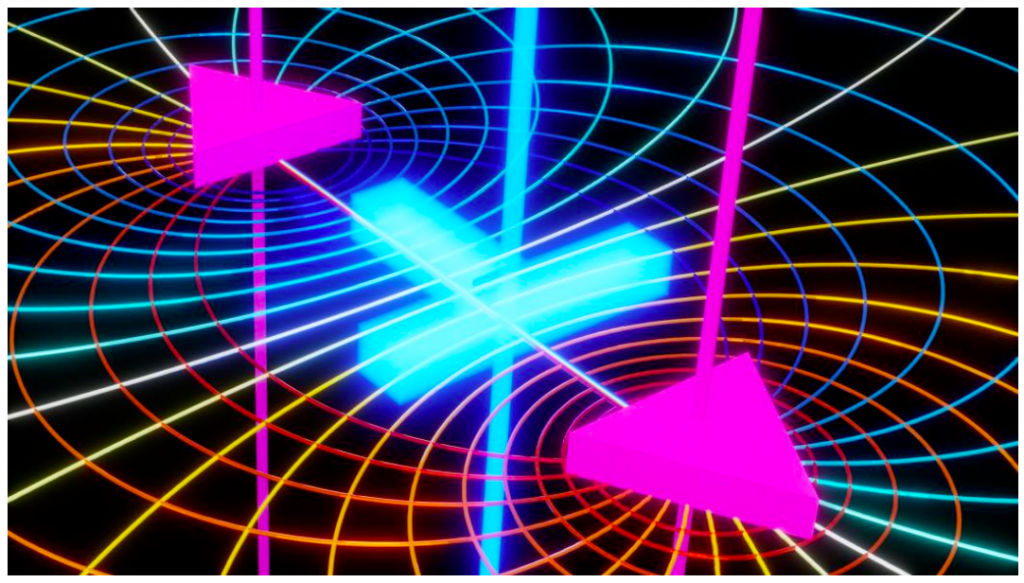【非線形力学領域・垂水 竜一 教授】
結晶欠陥の表裏一体関係の起源
-柔らかい幾何学による並進・回転欠陥の新しい見方-
 ・並進と回転を特徴とする二つの異なる結晶欠陥(※1)の間に指摘されてきた等価性の起源を解明
・並進と回転を特徴とする二つの異なる結晶欠陥(※1)の間に指摘されてきた等価性の起源を解明
・これまで、二つの欠陥を包括する理論的枠組みの整備は十分進められておらず、両者に同等のひずみ場が現れる根本的なメカニズムは未解明だった
・柔らかい幾何学「リーマン・カルタン多様体(※2)」に基づく統一理論の整備を進め、この課題を解決
・両者を幾何学的な共通の物差しで整理することが可能となり、近年注目されている回位による材料強化を理解する土台としての応用に期待
大阪大学大学院基礎工学研究科の小林舜典助教、大学院生の武政勝己さん(当時博士前期課程)、垂水竜一教授らの研究グループは、結晶中の「刃状転位」と「くさび回位」が等価なふるまいを示す仕組みを明らかにしました。両者は、規則的な原子配列からなる結晶に含まれた不規則な欠陥構造です。
欠陥の周囲に生じるひずみ場は結晶の強度や靱性を左右するため、材料科学分野での重要な研究対象とされています。これまで、一列に並んだ刃状転位の端部にくさび回位と同等のひずみ場が現れることは知られていましたが、その根本的なメカニズムは不明でした。
今回、研究グループは空間を柔軟にゆがませることのできる幾何学「リーマン・カルタン多様体」に基づく結晶欠陥理論の整備を進め、両者がアフィン接続(※3)と呼ばれる幾何学的構造のみで区別され、それ以外の骨組みが同一となることが、ひずみ場の等価性の起源であることを明らかにしました。さらに、同じ考え方は単独の刃状転位にも適用でき、正負のくさび回位双極子モーメントとして再解釈できることが分かりました。本成果は、優れた特性を持つ新しい結晶材料の設計方針に活用できると期待されます。
本研究成果は、英国科学誌「Royal Society Open Science」に、7月16日(水)8時(日本時間)に公開されました。
詳細は大阪大学ホームページ(ResOU)をご参照ください。
【用語説明】
(※1)結晶欠陥
理想的な結晶は規則的な原子配列からなるが、現実的には原子配列の規則性を破る様々な欠陥が多数内在している。原子配列の並進対称性を破る転位と、回転対称性を破る回位はその代表例である。いずれも対称性の破れた領域が線状に連なった線欠陥に分類される。
(※2)リーマン・カルタン多様体
平坦なユークリッド空間でのベクトルの内角(計量)と平行移動操作(アフィン接続)を一般化した空間の一種で、微分幾何学という数学を土台としている。空間の幾何学的な特徴は捩率と曲率という構造に代表される。結晶欠陥理論への応用は我が国の研究者である近藤一夫や甘利俊一らによって1950年代から進められた。この空間では転位を捩率、回位を曲率として表現することができる。
(※3)アフィン接続
リーマン・カルタン多様体上のベクトルの平行移動を記述する幾何学的構造。通常の平坦なユークリッド空間では、ベクトルを平行移動しても向きも大きさも変わらないが、リーマン・カルタン多様体上ではこれらが変化しうる。アフィン接続がその特性を決定している。
Last Update : 2025/07/31
最新記事
- 大阪大学 基礎工学部 機械工学同窓会 主催
卒業生と学生との交流会 エンジニアのキャリアパス勉強会 2025 (2025/09/16) - 研究室だより Vol.29 垂水研究室 (2025/07/31)
- 研究室だより Vol.28 垂水研究室 (2025/07/02)
- 令和6年度WEB総会のご案内 (2025/06/03)
- 大谷 智仁 准教授が令和7年度 科学技術分野の文部科学大臣表彰を受賞 (2025/05/21)